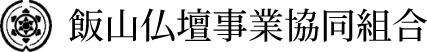長年培われた伝統の技で、心を込めて造る飯山仏壇。独特の「肘木組物(ひじきくみもの)」という技法や 金の箔押し、艶やかな蒔絵など 全てにわたって経験豊かな匠や伝統工芸士によって丁寧につくられています。このような飯山仏壇の品質をまもるため、厳しい品質表示の基準が設けられています。
また飯山仏壇の特徴のひとつは、数多くのパーツが精妙に組まれており、それを分解・補修して、きれいに洗って再び組み上げる「せんたく」です。この修理「せんたく」により、古い仏壇がよみがえり、数世代にわたって ご愛顧いただいてるお客様も沢山おります。
木地
木地には、ひめこ松、杉、檜、朴ノ木、桂などが使用され、朴ノ木は宮殿(くうでん)のみに使われます。厚い木をふんだんに使用するので、飯山仏壇は目方が重いといわれています。これらの木地を使って「本組み」をします。組立式といって、柱と台輪、柱と板が、雄、雌型によりしっかりと組合わされていますので、木材の伸縮や、振動、捩れ狂いがありません。本組みされた木地は、クサビを引抜くと組立てた逆の順序で簡単に分解できます。古くなった仏壇を分解し、部品を洗って再塗装「せんたく」し、新しく蘇らせることができるのです。

金具
金具は、銅または真鍮板を梅酢を使った独特の鍍金法で耐食性のあるものにし、傷がつかないように一度糊付けして加工されます。このため「せんたく」の際も再び梅酢鍍金して再使用することができます。

弓長押(ゆみなげし)
長押が弓型をしていることから弓長押と呼ばれ、飯山仏壇独特の「肘木組み」宮殿が、よく見える様に配慮され考案されたものです。彫刻師によって、伝統的な意匠が見事に彫り上げられています。

宮 殿(くうでん)
宮殿は「肘木組物」により造られ、飯山独特の技法です。肘木と組物が分解でき、「せんたく」が可能です。組物は、台肘木によって組立てられ、各層に肘木を通す穴と、飾り穴があり、肘木を通す穴にだけ、各種の肘木を一本づつ差し込んでゆきます。最後に化粧肘木を差し込んで肘木組物ができあがります。

箔押し(はくおし)
仕上げ拭きされた表面に、金箔を置き真綿で拭くと箔に美しい艶がでます。飯山仏壇はこの「艶出し箔押し方法」で金箔を置いているため、いつまでも美しい艶を保つことができるのです。

胡粉盛り蒔絵(ごふんもりまきえ)
胡粉盛りは蒔絵に立体感をもたせるために考え出された技法で、粒子が細かくて白いので盛った後の漆塗り、しべ書きが行い易く、きれいに仕上がる特徴をもっています。

塗
塗装は、下塗り研ぎ、中塗り研ぎして上塗り、または呂色漆塗りがされます。漆塗りを3回以上繰りかえして仕上がりです。